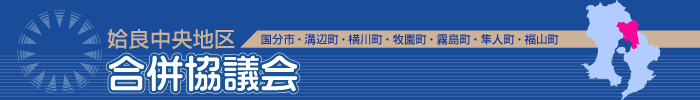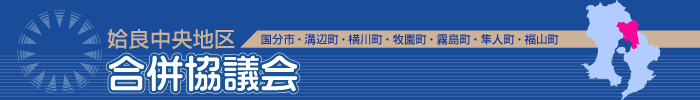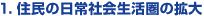 |
交通・情報通信手段の発達や経済活動の進展に伴い、住民の日常生活圏(通勤、通学、買物、医療等)は市町村の区域を越えてますます拡大しています。同時に行政サービスの提供を広域化することも可能になっています。これにあわせて市町村の行政体制を見直し、可能な限り拡大することが求められています。
|
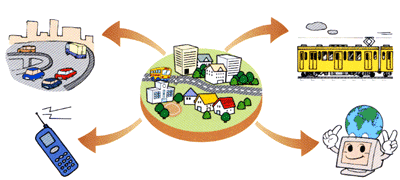 |
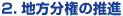 |
地方分権を推進するため、自己決定・自己責任の原則の下、住民に身近なサービスの提供は各地域で責任を持って選択することが求められます。そのためには、個々の市町村の自立・体制整備が必要になってきます。
これからは、個々の市町村において、政策を立案し、住民にわかりやすく説明することや、選択・実施される施策を裏付けるだけの税財政基盤などを充実することが求められます。
|
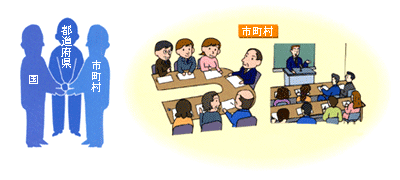 |
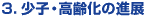 |
0歳から14歳までの年少人口の割合は年々減少し、平成12年に14.6%だったのが、平成42年には11.2%まで減少することが見込まれています。これに対し、65歳以上の老年人口の割合は、平成12年の17.4%から平成42年には29.6%まで増加することが予想されます。
このような少子・高齢化の進展は、特に中山間地などにある小規模市町村への影響が大きく、行政体制の再検討をしなければ、行政サービスのレベルの維持を図ることが困難になると予想されます。特に、福祉サービスなど、高齢社会に対応してより充実化が求められる行政分野については、従来の市町村の単位では、適切な対応が難しい状況になりつつあります。
|
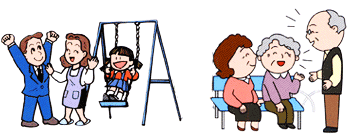 |
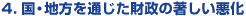 |
地方の借入金残高は、平成12年度末で約184兆円、国・地方を合わせた債務残高は、約642兆円(対GDP比125%)にのぼっています。
一般的に小規模市町村ほど税財政基盤は弱いのですが、合併により基盤を強化し、少子・高齢社会においても、期間的な行政サービスの提供に支障がないようにすることが望まれます。
|
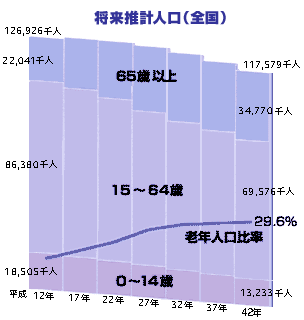 |
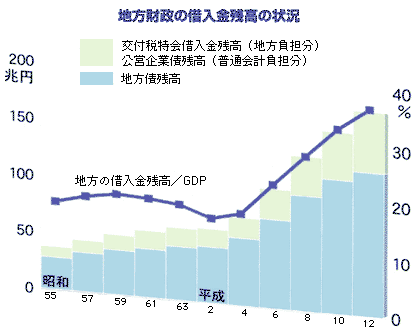 |